シン・ゴジラとスタッフも近いし、似たような雰囲気の映画になるのかと思っていたが、ちゃんと「ウルトラマン」だった。
ジャンルとしては「怪獣映画」のシン・ゴジラに対しシン・ウルトラマンは元々のテレビシリーズの軽さ、コミカルさも持たせた「特撮ヒーロー」と言える。
では作品全体の印象もシン・ゴジラよりも軽いものだったかというとそうではない。自分にとってはシン・ゴジラより心に響くものがあった。
一定の完成度を超えている映画であれば作品の評価は観る人の心の状態で変わる。どういうテーマに感動したか、どのシーンに感動したかで今の自分が何を求めているかが写し出される。
禍威獣(カイジュウ)が暴れる山間部、現場に逃げ遅れた子どもを発見した禍特対(カトクタイ)の神永新二は保護のため走る。
そこへ宇宙からすさまじい速度で光の巨人(ウルトラマン)が降着。その衝撃波で舞い上がる土砂、飛来する土石。神永は身を挺して子どもを救った。
自分の命とひきかえに子どもを救った人間の行動を不思議に思ったのか。ウルトラマンは神永と融合し、禍特対の面々と交流する。
初めは人間への好奇心と少しの懺悔だったのかもしれない。だが人間を知るにつれ(あるいは神永の心が残っており影響したのか)、それは愛に変わっていく。
圧倒的な力を持つウルトラマンが小さく非力な人間に憧れている。そして本質的な意味で人間を救おうとする。
憐憫ではない。人間の個々の力は小さいが群れになった時の力を認め期待もしている。
終盤、超巨大でとてつもない戦闘力を持つゼットンに、敵わないとわかっていながらも地球を守るため戦いを挑むウルトラマン。
胸を打つシーンだ。
もし劇場に来た子どもたちが「がんばえー!」と叫ぼうものなら号泣していたと思う。
自分のために生きる時代だ。
国のため会社のため誰かのためではない。自分らしく、自分の思い通りに生きよう。個を重んじ多様性を認めていこうという世の中だ。
もちろん個人の幸せを求める生き方は賛成だし自分もそう願う。その意味では良い時代になりつつあると思う。
だがこの追い風の中「自分本位」「利己」で何が悪いという主張も増えつつあるのも事実。
炎上しても注目されれば収益が上がるビジネスシステム。目的のためなら手段を選ばず。(私の苦手な言葉です)
国のためと言いながら私利私欲に走る政治家。職場や職業上の権限を悪用し私腹を肥やす上役たち。お手本となるべき人たちがこれでは下はバカらしくてやってらんねえとなる。道徳や倫理はどこかへ行く。
シン・ウルトラマンは、この尊厳が希薄となった世の中に、今だからこそ、ピュアなヒーローを描いたのだ。
クライマックス、人類の命運と神永(ウルトラマン)の命を選ぶ時、禍特対のリーダー田村は迷いなく部下の神永の命を優先する。(この田村の即断にも涙する)
だが神永は、人間を救えるなら自分は構わない、ときっぱりと言う。
自己犠牲を賛美する時代ではない。
しかし、利他の行動に崇高な美しさを感じるのは人間の実相だ。
ウルトラマンは行動で示す。恐れるな。誇り高くあれと。
禍威獣は漢字でわかるとおりコロナ禍だ。ベータカプセルをめぐる争いは核に象徴される強大な力を求める国の姿だ。
人類が危機に瀕している時もこのありさまかと。
人間、今こそ力を合わせる時だろうと。
一人ひとりは小さいが大きな知恵と力を生むはずだと。
見終わった後、数日ウルトラマンのことを考えるぐらいに心に響いた。
つまりは自分が今、求めていたのはピュアなヒーローだったということだ。
そんなにウルトラマンが好きになったのか、人間。
と、ゾーフィに言われると思う。
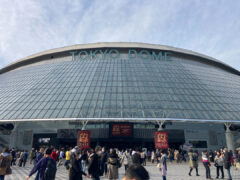





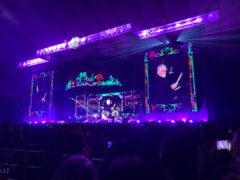

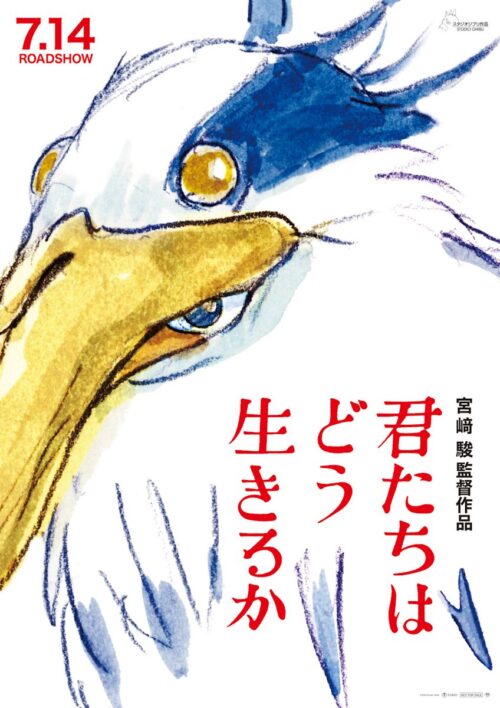
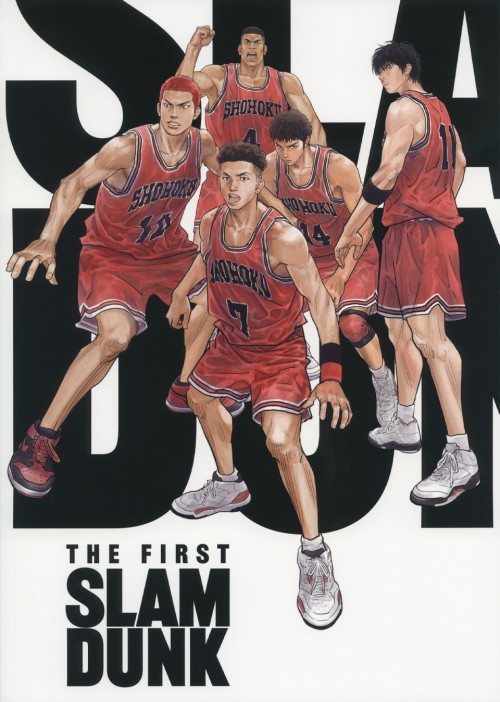
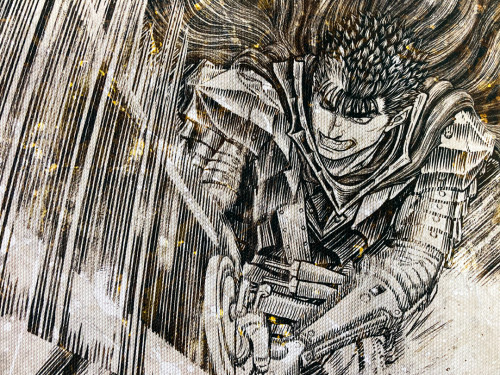


コメントをどうぞ